下にスライドして行って、見てくださいね。
SKYFON NV-7 27MHz 2022.03.25 追
1960年代後半〜1970年代頃に、国内では、玩具として販売されていた、27MHz帯を使用したトランシーバーです。
SKYFON と言うブランド名で、ネット検索すると、車載用CB機なども数種類ヒットします。
海外のサイトで掲載されている物が多いので、かなりの数、輸出されていたみたいです。
輸出仕様の物は、1957年のFCC規格 『 FCC Rule & Regulations Part15 』に準拠していますから、
終段入力 100mW以下となります。
送信出力だと、約50mWくらいでしょうか。
国内の規格を、かなり上回る送信出力となる可能性があります。
受信が、スーパーヘテロダイン式で、しかも水晶がピン足対応と言う事を売りにしています。
好きな周波数(チャンネル)に、簡単に変更できる嬉しい仕様です。
MASCOT や、バンダイ でも、同一の筐体を使用した物が発売されていたようです。 2022.04.04 追記
MASCOT NV-7 は、Armanax 様のサイトで大きな画像を見られます 。⇒ WALKIE TALKIE MASCOT
販売サイトのようなので、削除されていたらごめんなさい。
バンダイのTR-502 は 5石なので、中の基板は別物と思われます。
同じ筐体を使用した、STABO MULTIFON SUPER8 と言う名称の物があるようです。 2022.09.08 追記
トランジスタ8石、送信部も2ステージで、基板も別物のようです。
詳細は、Radio museum 様を参照願います。(回路図あり) ⇒ Multifon Super8
SKYFON ブランドの物で、8石の物も見つけました。 2022.09.29 追記
なぜか型番は、NV-7 のままになっています。
ebayのサイトで、画像が見られます。 ⇒ Skyfon 8Transistor
販売サイトなので、削除されていたらごめんなさい。

前面の筐体は、ダイキャストで出来ていて、かなり重いです。
ロッドアンテナの曲がりはありませんでしたが、1台 先端部分が取れていました。
外観の程度は、かなり良くて、メッキがキラキラと光っています。
SOLID STATE の表記が、年代を感じさせます。

電源は、006P-9V電池です。
ACジャックと記載がありますが、DC電源と記載して欲しい所です。
表示を信用して、交流をつないだら壊れます。
PTTの赤部分を押すと、PTTの青部分も、一緒に押し込まれるようになっていて
相手局に、ブザー音が送信されます。

電源スイッチと、ボリュームです。

背面のカバーは、薄くて華奢です。 ぶつけると、へこみます。
輸出機の場合は、背面に FCC などの型式銘板のような物が張り付けてあるようです。

ハンダ付けが綺麗で丁寧です。 2022年の時点で、約40年以上前の物ですが、ハンダ面が光っています。
基板に、NV-7 と、JAPAN の記載が見えます。 メードイン ・ ジャパン 良いですよね。

下記が、基板の説明と、各部の調整ポイントとなります。
CB帯で使用する場合は、任意の水晶をポン付けしただけで、そのまま使用できそうです。
缶トランジスタが6石で、1石だけ樹脂モールドタイプの物が使われています。
製造された年代を感じられますね。
送信のOSC回路に使われている、2SC711 トランジスタが、受信の際は、受信部のRF増幅&Mix部として動作しています。
珍しい兼用のさせ方だと思います。

下記の画像は、上からパターンを透視したようにする為に左右反転してあります。
基板のパターンから、回路を追って行ったのですが、なかなか大変でした。
ナショナル機のように、受信のOSC と Mix が兼用なのかな〜と、思ったら全く違っていました。
回路の把握に使用した画像 ⇒ 書き込みのある画像

受信部の RF増幅&Mix回路 ですが、トランジスタの使われ方が、下記のような接続となっていました。
2SC711 のベースに、RX-OSCの出力が接続されています。
( イメージです。実際の回路を書き出した物ではありません。)

水晶を28MHz帯の物に交換して、送受信の各コイル・コアを調整すると、
簡単に、28MHzAM 実験機に出来そうです。
受信がスーパーヘテロダイン式なので、超再生式の物よりも交信距離が伸びそうですね。
山頂〜山頂など、障害物が無い条件だと、DX も狙えるかも。
基板のパターンから、回路を把握しています。
記載内容が間違っている場合もありますので、ご了承願います。
( 注意事項 )
上記トランシーバーが、製造・販売されていた時期に
適用されていた電波法のレギュレーションと、現在の内容では相違があります。
微弱無線局の規格や、静的動作時における不要輻射などの規格を見ると
ここで紹介したトランシーバーのほとんどは、使用できない可能性が高いと思われます。
免許が不要な微弱無線局として使用する場合は、現行の電波法を逸脱しないように お願い致します。
『 当該無線局から 3mの距離において その電界強度が 500μV/m 以下のもの 』 と言う規則があります。
送信機の出力が○○mW以下 と言うような電力値での規制ではなく、電界強度で測定した値である事に注意が必要です。
下記は、Wiki 微弱無線局に記載されている、新・旧規則の違いを、分かり易くした表となります。
新規則に対応した、微弱無線局は、旧規則と同じ15μV/m で比較すると、到達距離が短くなっているのが分かります。
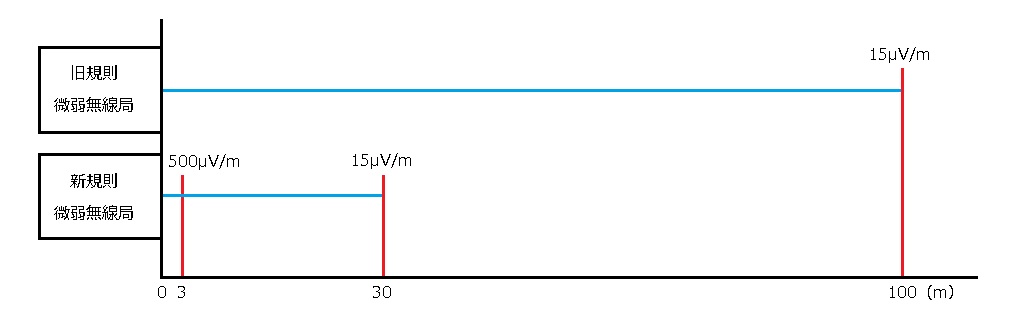
連絡用途などで、実際に使用される場合は、自己責任にてお願い致します。
詳しくは、こちらをご覧下さい。 ⇒ 総務省 微弱無線局の規定
⇒ Wiki 微弱無線局
受信回路が超再生方式の場合、受信しているだけでも、
アンテナから、不要輻射(不要な電波)を発射してしまいます。
( 微弱無線局、考え方の例として )
特定小電力トランシーバーは、出力10mW ですが、技適の認証を受けています。
周波数により、しきい値は違いますが、10mW の出力でも 技適が無ければ違法となります。
つまり、微弱無線局の規定が改正されてから、無許可で使用できるトランシーバーの送信出力は、
かなり微弱な小電力になると考えた方が良いと思います。
不定期ではありますが、続きをUPして行きたいと思っています。
記載間違い等がありましたら、ご連絡をお願い致します。
前のページに戻る