下にスライドして行って、見てくださいね。
Sメーターが無い CB機の受信部を調整する場合。(2025.06.08 追加)
検波後の電圧を、テスターなどで測定します。
このテスターの指針がSメーターの代わりとなります。
これを見ながら 受信部のコイルコアを調整します。
測定する箇所について。
測定する箇所は、どのCB機でも 検波ダイオードの出力とGND間 又は、
音声ボリュームの両端端子になります。
測定中は、ボリュームを回さないで下さい。
デジタルテスターだと、表示がパラパラと変化して見ずらいです。
DC低電圧が測定できるアナログテスターを使用するか、
ジャンクCB機から外した アナログSメーター+可変抵抗 などを接続した方が
調整し易いと思います。
下記は、National RJ-7 の場合となります。
回路図で、● 赤丸印の部分が測定箇所となります。
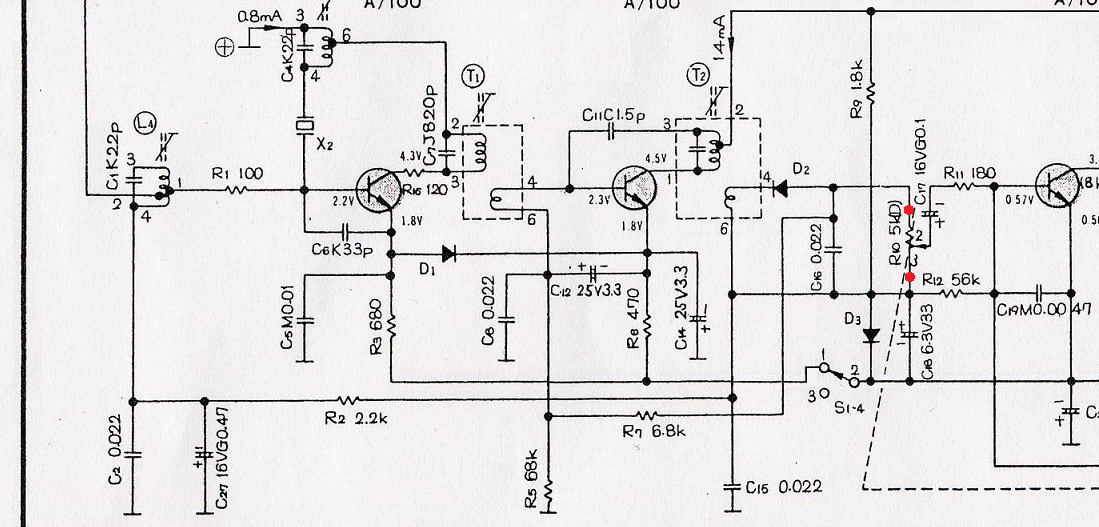
下記の画像で 青線が接続されているボリュームの両端に、
ダイオードD2 で検波された電圧が出ています。
この部分に、テスターの測定端子を接続します。
デジタルテスターの場合は、極性を気にしなくてもOKです。
アナログテスターや、ジャンクCB機から外した Sメーター+可変抵抗 を接続する場合は、
左側の青線が+となります。
なお、受信信号が無いと、電圧は変化しません。
つまり、ノイズを頼りにした調整は出来ません。
無信号時は、−40mV位ですが、受信時は400mV位の電圧に
大きく変化するので分かると思います。
ピーク電圧になるように、各コイルコアを調整します。
上記を参考にして、改造・修理などする場合、自己責任にてお願い致します。
不明な点、間違いなどがあれば、ご連絡下さい。
前のページに戻る